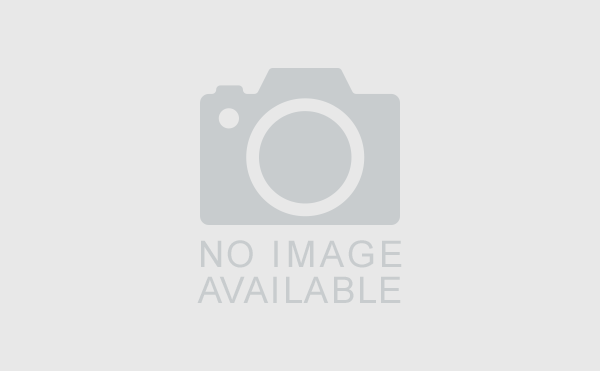ケーブルラックとは何か?敷設方法や注意点などをご紹介
こんにちは。シルバ電設のブログをご覧いただきありがとうございます。当社では新築オフィスビルの電気工事を多く手がけており、幹線工事や分電盤まわりの配線を含む大規模な設備工事を得意としています。
今回は、電気配線に欠かせない「ケーブルラック」について解説します。幹線引きの記事でも少し触れましたが、ケーブルラックは太い電線や多量の配線を支える骨組みのような存在です。普段は天井裏などに隠れていることが多いですが、その重要性は非常に高いです。
ケーブルラックとは?

ケーブルラックとは、電気ケーブルや通信ケーブルなどをまとめて支えるための金属製の支持材(配線経路)です。建物の構造体(梁や壁、天井など)に取り付けられ、電線を効率よく、かつ安全に通すために使用されます。
形状にはいくつか種類がありますが、代表的なものは以下の通りです:
- パンチングラック(穴あきタイプ)
→ 軽量で通気性が良く、建築現場でよく使われます - メッシュラック
→ 通信系や弱電系に多く、自由度の高い配線が可能 - トレイ型ラック(トラフ)
→ 荷重が大きく耐久性に優れ、幹線ケーブル向き
ケーブルラックの選定は、**通すケーブルの本数・重量・設置環境(屋内/屋外・温度・湿気)**に応じて慎重に決める必要があります。
ケーブルラックの敷設方法
では、実際の現場でどのようにケーブルラックを敷設しているのか、その流れをご紹介します。
1. ルート設計・墨出し
まずは配線ルートの設計です。設計は私たちでなく元請けの企業の担当者が行い、天井裏、梁下、電気室内などにどのような経路でラックを設置するかを決定、図面を作成します。私たちはその図面に従って墨出し(実際の取り付けラインを床や壁にマーキング)を行います。
2. 吊りボルト・支持金具の取り付け
ケーブルラックは、天井や梁から「吊りボルト(全ネジ)」と呼ばれる細長い金属の棒のような支持金具で吊り下げる形で固定されることが多いです。吊りボルトを天井につけるために、天井にアンカードリルで穴をあけてアンカーを付け、そこに釣りボルトをネジの様にねじ込んで固定します。吊りボルトの位置や高さは事前にしっかりレーザーなどを使ってレベル出し(水平確認)をしてラックがきちんと図面の寸法通り設置できるようにします。
3. ケーブルラックの据え付け・連結
ラックの部材(1~2mほど)を現場で組み立てながら取り付けます。継ぎ手(ジョイント)を使って連結し、ネジでしっかり固定。重量があるため、脚立や足場、安全帯を使用して慎重に作業します。
4. アース接続(接地)
金属製のラックには、感電や漏電防止のためにアース(接地)工事が必要です。ラック同士をボンディング(導通させる)し、適切な位置で接地線を取ります。
5. 配線・ケーブル敷設
最後に、ラックに沿って電線を敷設していきます。配線中のたるみや交差、重なりに注意し、結束バンドなどで適切に固定します。
ケーブルラック敷設の注意点

● 落下防止・安全対策
ラックは高所での作業が多く、重い金属製の部材を扱うため、落下事故には特に注意が必要です。足場や墜落防止器具の使用、ヘルメット・保護手袋の着用は必須です。
● 荷重・支持間隔の確認
設置するケーブルの本数や重さに応じて、支持点の間隔を適切に調整する必要があります。間隔が広すぎると、ラックがたわみ、ケーブルに悪影響を及ぼします。
● 可動部・ダンパーとの干渉
空調設備や防火ダンパー、照明器具などと干渉しないよう、事前に他業種との取り合いを確認しておきましょう。特に天井内はスペースが限られているため、施工前の調整が非常に重要です。
ケーブルラックは「配線の基盤」

ケーブルラックは、電気工事において「配線の道」として非常に重要な役割を果たします。特にビルや大規模施設では、幹線ケーブルの重量や本数が多くなるため、ラックの設計・施工が建物全体の電力供給の安定性に大きく関わってきます。
弊社では、電気設備工事の設計から施工、そして幹線の敷設やケーブルラック工事まで一貫して対応可能です。現場に合わせた最適な施工をご提案し、安全第一・品質重視で工事を行っております。
電気設備のご相談や施工依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください!